公的年金の給付の種類
日本の公的年金は、20歳以上60歳未満が全員加入する国民年金と、会社員や公務員等が加入する厚生年金保険の2階建てで制度が作られています。大きく「老齢」「障害」「遺族」の3種類です。
| 国民年金法 | 厚生年金保険法 | 要 件 |
|---|---|---|
| 老齢基礎年金 | 老齢厚生年金 | 65歳到達等 |
| 障害基礎年金 | 障害厚生年金 | 病気やケガで一定の障害 |
| 遺族基礎年金 | 遺族厚生年金 | 生計維持の被保険者が死亡等 |
条文を見てみよう
第15条(給付の種類)
この法律による給付は、次のとおりとする。
一 老齢基礎年金
二 障害基礎年金
三 遺族基礎年金
四 付加年金、寡婦年金及び死亡一時金
老齢が支給事由の老齢基礎年金
障害が支給事由の障害基礎年金
死亡が支給事由の遺族基礎年金
そして、「第1号被保険者」期間だけの独自給付である、付加年金、寡婦年金及び死亡一時金、さらに法附則の方で、特別一時金と脱退一時金があります。
基本権と支分権
基本権(受給権)とは、年金を受けることができる基本的な権利そのものをいい、支分権とは、基本権に基づき、各支払期月に年金の支給を受ける権利のことをいいます。
基本権は要件をみたすと、法律上当然に生じます。老齢基礎年金で例えると、受給資格期間(10年以上)を満たしたものが、65歳に達したら発生します。
一方、支分権(支給を受ける権利)を得るためには、要件が満たされているという確認を受ける裁定請求が必要です。基本権は生じていても裁定請求しないと年金の支給を受けることは出来ないんです。
条文を見てみよう
第26条(老齢基礎年金の支給要件)
老齢基礎年金は、保険料納付済期間又は保険料免除期間(学生納付特例及び保険料納付猶予制度の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。)を有する者が65歳に達したときに、その者に支給する。ただし、その者の保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年に満たないときは、この限りでない。
第16条(裁定)
給付を受ける権利は、その権利を有する者の請求に基いて、厚生労働大臣が裁定する。
26条は基本権のことが書いてあります。保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年以上あるものが、65歳に達したら老齢基礎年金を支給する。
基本権と支分権は、年金対策上重要な論点で、しっかりと理解する必要があります。条文に書いてありますが「支給する」=「基本権(受給権)」の事を示しています。問題で「支給する」と問われていたら基本権(受給権)の事を聞いているんだなぁと判断して下さい。
また「支給を開始する」とか「支給を始める」と問われたら、それは「支分権」の事を聞いています。要件を満たし基本権が当然に生じても、請求しないと支給は開始されません。請求し基本権があることの確認がされたら年金裁定通知書と年金証書が送られてきて、年金の支給が開始されます。
年金給付の支給期間は?
基本権を有した人が、裁定請求したら年金給付の支給が開始されます。では支払期日はどうなっているのでしょうか?年金なので支給額は「年額」なのですが偶数月の6回に分けて支払われます。
条文を見てみよう
第18条(年金の支給期間及び支払期月)
年金給付の支給は、これを支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月から始め、権利が消滅した日の属する月で終るものとする。
2 年金給付は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた日の属する月の翌月からその事由が消滅した日の属する月までの分の支給を停止する。ただし、これらの日が同じ月に属する場合は、支給を停止しない。
3 年金給付は、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の6期に、それぞれの前月までの分を支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであつた年金又は権利が消滅した場合若しくは年金の支給を停止した場合におけるその期の年金は、その支払期月でない月であつても、支払うものとする。
- 年金は、その事由が生じた日の属する月の翌月から権利が消滅した日の属する月まで月を単位として支給される。
- 年金の停止は、その事由が生じた日の属する月の翌月から権利が消滅した日の属する月まで月を単位として支給停止される。ただし、同月内で停止事由が止んだ場合は支給停止されない。
- 毎年、偶数月に前月までの分を6期に分けて支払われる。
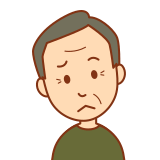
5月3日に65歳の誕生日を迎えるんですが、いつ年金もらえるの?
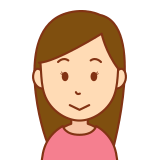
早ければ8月15日にもらえますよ
太郎さんは、65歳に達するのは誕生日の前日の5月2日です。つまり5月2日に基本権が生じます。そして支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月から開始されますので支払い対象月は6月からとなります。「偶数月に前月までの分」が支払われますので、最初の支給は「6月と7月」の2か月分が8月15日に支給されます。偶数月に支払われるのが原則ですが、初回は手続きの関係上、時間を要しますので場合によっては9月15日と奇数月に支払われることもあります。
条文18条3項の「ただし、前支払期月に支払うべきであつた年金又は権利が消滅した場合若しくは年金の支給を停止した場合におけるその期の年金は、その支払期月でない月であつても、支払うものとする。」に該当します。
1日が誕生日の人は・・・
太郎さんが5月1日生まれだった場合はどうなるでしょうか?
事例問題で1日生まれの人が、現れたら要注意です。なぜなら誕生日の前日に歳をとるから。なぜ前日なのかは、こちらの記事をご覧ください。
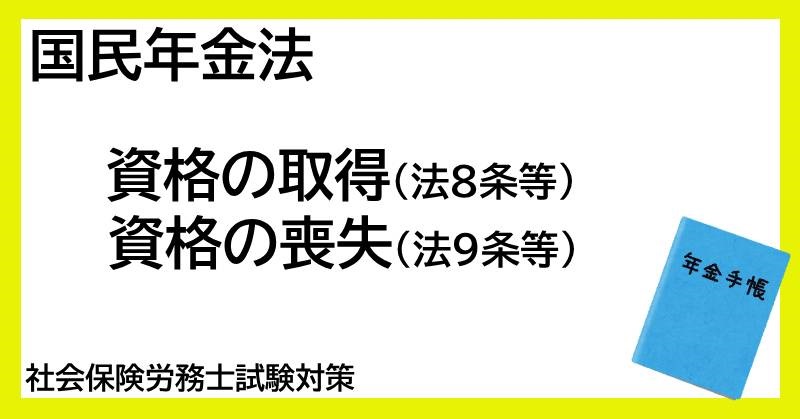
5月1日生まれの人は、4月30日に65歳に到達し基本権が生じます。そして支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月から開始されますので支払い対象月は5月からとなります。同じ5月生まれなのに1日生まれの人は1月分多くもらえます。お得? 被保険者期間を計算するうえでも重要ですので1日生まれは気にして下さい。
支払額の端数はどうなるの?
年金は年額で計算されますが、支払いは月を単位として偶数月に前月までの分を6期に分けて支払われます。その計算上1円未満の端数が生じたら、どう処理されるのでしょうか?
条文を見てみよう
第18条の2(2月期支払の年金の加算)
前条第3項の規定による支払額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
2 毎年3月から翌年2月までの間において前項の規定により切り捨てた金額の合計額(1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)については、これを当該2月の支払期月の年金額に加算するものとする。
前条第3項とは、6期に分けて支払う規定でしたね。各支払期月の支給額の1円未満の端数は「一旦」切り捨てられます。で、切り捨てられた端数は合計されて(6期分)当該2月に支払期日の年金額に加算されます。
失権
第29条(失権)
老齢基礎年金の受給権は、受給権者が死亡したときは、消滅する。
老齢基礎年金の受給権は、受給権者が死亡したときに失権します。老齢基礎年金の受給権が失権するのは、受給権者が死亡したときのみとなります。海外に移住しても日本国籍を失っても失権しません。
それでは過去問いきましょう
問1. 国民年金法によれば、給付の種類として、被保険者の種別のいかんを問わず、加入実績に基づき支給される老齢基礎年金、障害基礎年金及び遺族基礎年金と、第1号被保険者としての加入期間に基づき支給される付加年金、寡婦年金及び脱退一時金があり、そのほかに国民年金法附則上の給付として特別一時金及び死亡一時金がある。
過去問 令和2年 国民年金法
問2. 付加年金、寡婦年金及び死亡一時金は、第1号被保険者及び第3号被保険者としての被保険者期間を対象とした給付で、第2号被保険者としての被保険者期間は対象とされない。
過去問 平成19年 国民年金法
問3. 毎支払期月ごとの年金額の支払において、その額に1円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てるものとされているが、毎年4月から翌年3月までの間において切り捨てた金額の合計額(1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)については次年度の4月の支払期月の年金額に加算して支払うものとされている。
過去問 平成28年 国民年金法
問4. 年金給付の支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた日の属する月の翌月からその事由が消滅した日の属する月までの分の支給を停止する。ただし、これらの日が同じ月に属する場合は、支給を停止しない。
過去問 平成22年 国民年金法
問5. 老齢基礎年金の支給を停止すべき事由が生じた日の属する月の翌月にその事由が消滅した場合は、当該老齢基礎年金の支給を停止しない。
過去問 令和元年 国民年金法
基本権と支分権は、確実に理解しましょう。「基本権」は年金を受けることができる基本となる権利で、「支分権」は基本権に基づき支払い期日ごとに支払われる年金の支給を受ける権利でした。時効の起算日も違います。繰上げは「請求」しますが、繰下げは「申し出」です。繰上げする人は、まだ基本権が生じていないので請求することで基本権を発生させます。繰下げする人は、基本権は既に生じていますので申し出なんです。繰上げ、繰下げについては別の記事で解説します。ご覧いただきありがとうございました。
この記事が参考になったら応援お願いします。↓


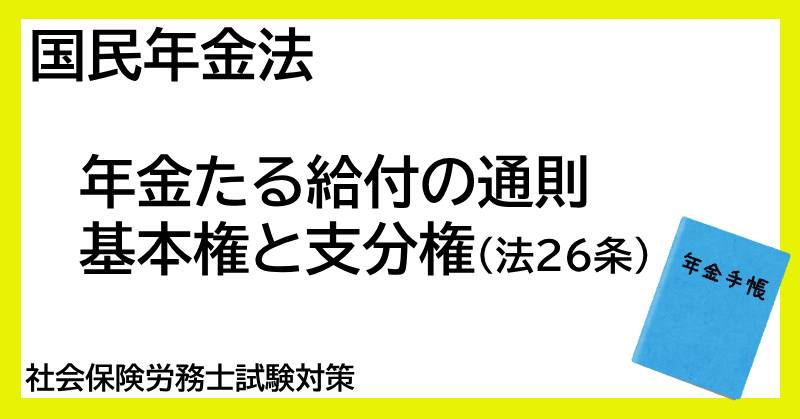
コメント
コメント一覧 (2件)
問4の過去問平成22年度8Dで1月停止されると勘違いしてなかなか正解できない。テキスト再確認してもそのまま書いてあるが。
ありがとうございます📕
私は問5の令和元年の方が、よくひっかかります💦