老齢基礎年金の繰上げとは?
「老齢基礎年金は、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年以上あるものが、65歳に達したときに支給する」と法26条にあるように、受給開始年齢は、原則65歳です。しかし本人の希望で60歳から64歳の間で選ぶことが出来ます。これを支給の繰上げといいます。
条文を見てみよう
法附則第9条の2(老齢基礎年金の支給の繰上げ)
保険料納付済期間又は保険料免除期間を有する者であつて、60歳以上65歳未満であるもの(任意加入被保険者でないものに限る。)は、当分の間、65歳に達する前に、厚生労働大臣に老齢基礎年金の支給繰上げの請求をすることができる。ただし、その者が、その請求があった日の前日において、その者の保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年に満たないときは、この限りでない。
2 前項の請求は、厚生年金保険法の老齢厚生年金の規定により支給繰上げの請求をすることができる者にあつては、当該請求と同時に行わなければならない。
3 第1項の請求があつたときは、その請求があつた日から、その者に老齢基礎年金を支給する。
4 前項の規定により支給する老齢基礎年金の額は、本来の老齢基礎年金の額から政令で定める額を減じた額とする。
5 寡婦年金の受給権は、受給権者が第3項の規定による老齢基礎年金の受給権を取得したときは、消滅する。
老齢基礎年金の受給資格期間(10年)を満たした60歳以上65歳未満のものは、厚生労働大臣に支給繰上げの請求ができます。
任意加入被保険者は支給の繰上げが出来ません。任意加入は受給権が発生するまでの間、満額の480月に満たない人が、年金額を増やす為に加入しています。支給繰上げは請求によって「受給権」を発生させますので任意加入被保険者は支給繰上げをすることはできないのです。任意加入被保険者についての記事はこちら↓
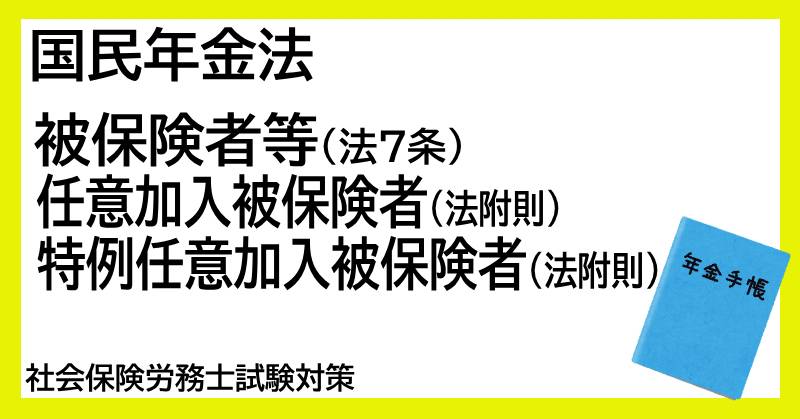
2項を見てみましょう。厚生年金保険法の老齢厚生年金を支給繰上げできる人は、同時に支給繰上げをしないといけません。片方だけ繰上げ出来ないんですね。別の記事であげますが、支給繰下げは別々に申出が可能です。
3項の「請求があつたときは、その請求があつた日から、その者に老齢基礎年金を支給する」とは、請求のあった日に受給権が生じるという意味で、実際の支給は受給権が生じた日の属する月の翌月から開始されます。「支給する」とは受給権発生の事でしたね。受給権と支分権の記事はこちら↓
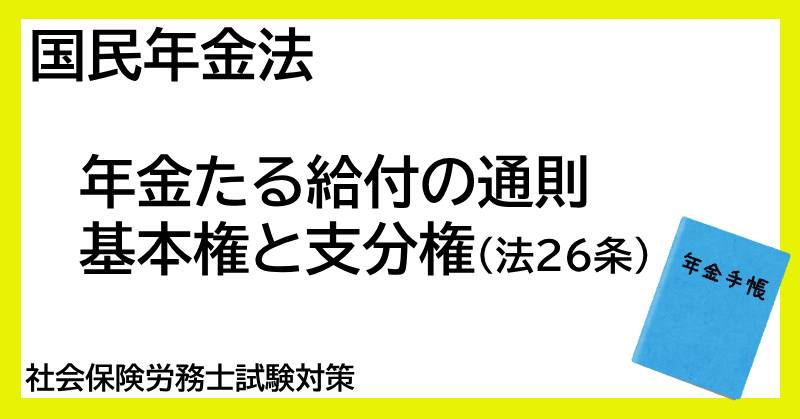
政令で定める額を減じた額とは?
支給繰上げを請求し、早く年金を貰おうとすると減額されて生涯にわたり支給されます。どれくらい減額されるのでしょうか?
老齢基礎年金の支給繰上げ請求をしたら、本来の老齢基礎年金の年金額に減額率を乗じた額に減額されます。「減額率」とは、1,000分の4に支給繰上げを請求した日の属する月から65歳に達する日の属する月の前月までの月数を乗じて得た率をいいます。
例えば60歳に達した日の属する月に繰上げの請求をすると、65歳に達する日の属する月の前月までの月数は60月となりますので減額率は、60×0.004=0.24となり24%減額されます。
減額率は1月(0.4%)から60月(24%)の範囲になりますね。
0.004✕繰上げ請求月から65歳到達月の前月までの月数
なお減額率に使用されている1,000分の4は令和4年4月1日に法改正された数字ですので、この規定が適用されるのは、令和4年4月1日の前日において60歳に達していない人になります。法改正前は1,000分の5でした。つまり昭和37年4月2日以降生まれの人が1,000分の4で昭和37年4月1日以前生まれの方については、1,000分の5となります。
寡婦年金の受給権は消滅する
寡婦年金の受給権を有している人が、支給繰上げをすると寡婦年金の受給権は消滅します。また支給繰上げ請求した人には寡婦年金は支給されません。
寡婦年金は、国民年金の第1号被保険者として加入していた夫を亡くした妻自身の老齢基礎年金を65歳になって受給できるまでのつなぎとして受ける年金です。自分の意志で老齢基礎年金を繰上げしてしまうと、65歳に達したとみなされて寡婦年金は支給されません。寡婦年金についての記事はこちら↓
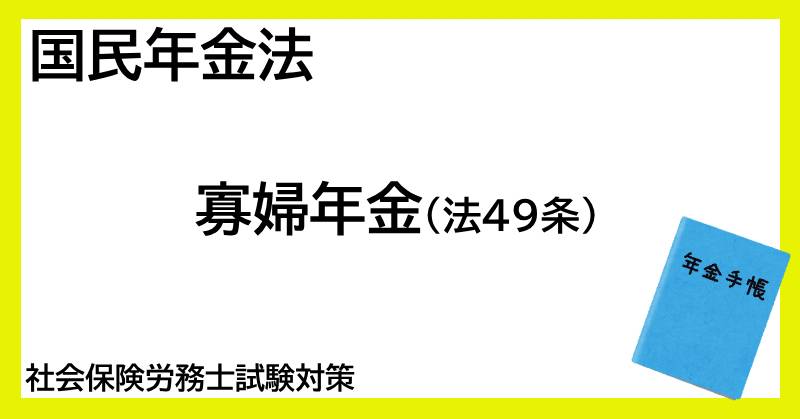
支給繰上げを請求すると・・・
支給繰上げをすると、65歳に達したとみなされて寡婦年金は支給されませんが、他にも制約がありますので紹介しておきます。
- 事後重症、基準傷病、その他障害による障害基礎年金は支給されません
- 国民年金の任意加入被保険者になれなくなります
- 保険料の追納ができなくなります
それでは過去問いきましょう
問1. 繰上げ支給の受給権は、繰上げ請求のあった日の翌日に発生し、受給権発生日の属する月の翌月から支給される。
過去問 平成23年 国民年金法
問2. 繰上げ支給を受けると、寡婦年金は支給停止される。
過去問 平成23年 国民年金法
問3. 昭和37年4月20日生まれの者が、令和6年4月25日に老齢基礎年金の支給繰上げの請求をした場合において、当該支給繰上げによる老齢基礎年金の額の計算に係る減額率は、14.4%である。
過去問 令和元年改題 国民年金法
令和と平成は簡単です。下1桁がそのまま平成となります。平成に「63」を足すと昭和になります。
令和6年=平成36年
平成36年=昭和99年
昭和99年ー昭和37年=62となり62歳に支給繰上げ請求をしたことが分かります。
・支給の繰上げを請求した日の属する月・・・令和6年4月
・65歳に達する日の属する月の前月・・・・・令和9年3月
3年(36月)ですね。0.004×36=0.144で14.4%の減額です。
問4. 支給繰上げの請求をした場合は、付加年金についても同時に繰上げ支給され、老齢基礎年金と同じ減額率で減額される。
過去問 平成26年 国民年金法
問5. 支給繰上げした場合の減額率について、昭和26年4月1日以前に生まれた者の減額率は年単位、昭和26年4月2日以後に生まれた者の減額率は月単位になっている。
過去問 平成26年 国民年金法
支給繰上げは、請求によって受給権を発生させ65歳より前に、老齢基礎年金を受給する制度でした。なお支給繰下げは「受給権」を有していますので、請求では無く「申出」で行います。減額率は「繰上げ請求月から65歳到達月の前月までの月数」ですので事例問題が出題されたときは注意して下さい。
この記事が参考になったら応援お願いします。↓


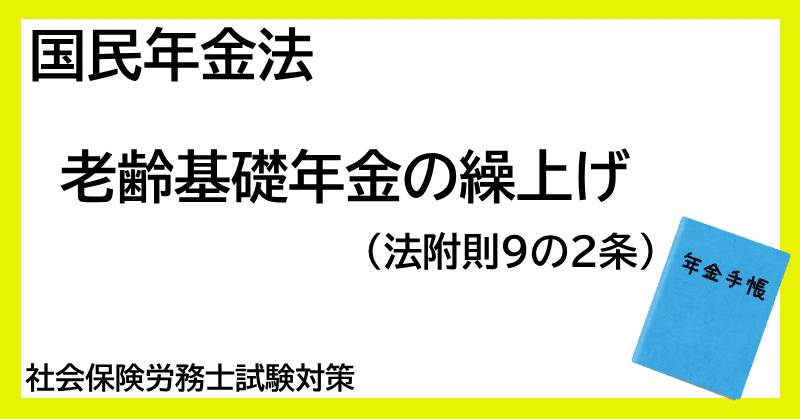
コメント