学生納付特例とは?
日本に住所を有する20歳以上60歳未満は国民年金に強制加入ですが、平成3年3月まで学生は任意でした。平成3年4月からは加入が義務となり親元世帯の所得により免除の規定があったものの、学費や仕送りもあり親が保険料を負担するのも大変・・・そこで平成12年4月に学生本人の所得が一定額以下なら納付を要せず、社会にでてから追納で納付する形の制度(学生納付特例)が誕生しました。
条文を見てみよう
第90条の3(学生納付特例)
次の各号のいずれかに該当する学生等である被保険者又は学生等であつた被保険者等から申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間(学生等である期間又は学生等であつた期間に限る。)に係る保険料につき、既に納付されたものを除き、これを納付することを要しないものとし、申請のあつた日以後、当該保険料に係る期間を保険料全額免除期間(追納が行われた場合にあつては、当該追納に係る期間を除く。)に算入することができる。
一 当該保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得(1月から3月までの月分の保険料については前々年の所得とする。以下同じ)が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額以下であるとき。
二 被保険者又は被保険者の属する世帯の他の世帯員が生活保護法による生活扶助以外の扶助受けるとき。
地方税法に定める障害者、寡婦その他の同法の規定による市町村民税が課されない者として政令で定める者であって、当該保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得が135 万円以下であるとき。
三 保険料を納付することが著しく困難である場合として天災その他の厚生労働省令で定める事由があるとき。
以下の要件のいずれかに該当する被保険者(被保険者であった者)から申請があったときには、厚生労働大臣は、その指定する期間に係る保険料を納付することを要しないこととすることができます。
- 保険料免除月の属する年の前年(1~3月までは前々年)の所得が政令で定める額以下
- 被保険者または世帯員が、生活保護法の生活扶助以外の扶助などを受ける
- 地方税法に定める障害者または寡婦およびひとり親で、前年の所得が135万円以下
- 保険料を納付することが困難であるとして、天災その他の厚生労働省令で定める事由がある
政令で定める額の所得とは
128万円+38万円(原則)×扶養親族等の数
となっていて単身世帯では式にあてはめると128万円になります。
申請免除の要件と違い、本人についてのみ所得の要件が問われます。世帯主や配偶者には所得要件が問われません。
所得要件については、他の申請免除と横断して整理しましょう。128万は半額免除と同じです。←「学生は半人前」で覚えました。
申請免除についての記事はこちら
学生納付特例は、他の申請免除に優先して適用されます。よって他の申請制度は受けることが出来ません。法定免除が適用される場合は、法定免除が優先します。
法定免除>学生納付特例>申請免除
対象の学生は?
学校教育法に規定する大学(大学院含む)、短大、高校、高専、専修学校、各種学校(修業年限が1年以上の課程に限る。)等に在学する20歳以上の学生です。年齢制限はありませんので第1号被保険者である20歳以上60歳未満であれば申請できます。
なお、昼間部だけに限らず、夜間・定時制課程・通信課程の学生も対象です。
老齢基礎年金との関係は?
学生納付特例期間は、老齢基礎年金の受給資格期間(10年)には算入しますが、年金額の計算には反映されません。卒業してから10年以内に追納する必要があります。保険料免除期間としては扱われますが、年金額の計算に入らないんです。
第28条 (支給要件)
老齢基礎年金は、保険料納付済期間又は保険料免除期間(学生納付特例及び納付猶予の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。)を有する者が65歳に達したときに、その者に支給する。
ただし、その者の保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年に満たないときは、この限りでない。
卒業以外で学生等でなくなったときは?
学生の保険料納付特例の申請を行い承認された者が、承認期間中に学校を退学した場合は、学生納付特例不該当届を機構に提出しなければいけません。その場合、学生であった月の翌月分から保険料の納付義務が発生します。学生でなくなった原因が卒業であるときは学生納付特例不該当届の提出は不要です。
学生納付特例の事務手続き
学生納付特例の申請手続きをしやすくするよう、学生納付特例事務法人が代行を行う制度があります。
第109条の2の2(学生納付特例の事務手続に関する特例)
国及び地方公共団体並びに国立大学法人法に規定する国立大学法人、地方独立行政法人法に規定する公立大学法人及び私立学校法に規定する学校法人その他の政令で定める法人であって、厚生労働大臣がこれらの法人からの申請に基づき、第90条の3第1項(学生等の保険料の納付特例)の申請(以下この条において「学生納付特例申請」という)に関する事務を適正かつ確実に実施することができると認められるものとして指定するもの(以下「学生納付特例事務法人」という)は、その設置する学校教育法に規定する大学その他の政令で定める教育施設において当該教育施設の学生等である被保険者(以下この条において「学生等被保険者」という)の委託を受けて、学生等被保険者に係る学生納付特例申請をすることができる。
大学等の教育施設で学生納付特例の申請を代行を行える規定になります。
- 学生納付特例申請の事務が行えるのであって「保険料の納付」に関する事務は行えません。
- 学生等被保険者が学生納付特例事務法人に学生納付特例申請の委託をしたときは、当該委託をした日に、学生納付特例申請があったものとみなされます。
- 納付猶予制度は時限措置ですが、学生納付特例は時限措置ではありません。
- 所得の額は本人についてのみ問われます。
- 他の申請免除に優先して適用されますが、法定免除の方が優先されます。
保険料納付猶予制度
就職が困難であったり失業中の若者は所得のある親と同居していたら、世帯主は、その世帯に属する被保険者の保険料を連帯して納付する義務を負いますので免除の対象にはなっていませんでした。そこで30歳未満の者を対象にした納付猶予制度ができたのですが現在は年齢が50歳未満まで拡大されています。
以下の要件のいずれかに該当する被保険者(被保険者であった者)から申請があったときには、厚生労働大臣は、その指定する期間に係る保険料を納付することを要しないこととすることができます。
- 保険料免除月の属する年の前年(1~6月までは前々年)の所得が政令で定める額以下
- 被保険者または世帯員が、生活保護法の生活扶助以外の扶助などを受ける
- 地方税法に定める障害者または寡婦およびひとり親で、前年の所得が135万円以下
- 保険料を納付することが困難であるとして、天災その他の厚生労働省令で定める事由がある
政令で定める額の所得とは
35万円×(扶養親族等の数+1)+32万円
となっていて単身世帯では式にあてはめると67万円になります。
申請免除の要件と違い、本人と配偶者についてのみ所得の要件が問われます。世帯主には所得要件が問われません。自立できる大人なので親の所得は関係ないと言った所でしょうか?所得の額は全額免除と同じですね。他の免除申請等と横断で整理しましょう。
| 種類 | 政令で定める額 | 所得要件 |
| 申請全額免除 | 35万円×(扶養親族等の数+1)+32万円 | 本人、世帯主、配偶者 |
| 申請4分の3免除 | 88万円+38万円(原則)×扶養親族等の数 | 本人、世帯主、配偶者 |
| 申請半額免除 | 128万円+38万円(原則)×扶養親族等の数 | 本人、世帯主、配偶者 |
| 申請4分の1免除 | 168万円+38万円(原則)×扶養親族等の数 | 本人、世帯主、配偶者 |
| 納付猶予制度 | 35万円×(扶養親族等の数+1)+32万円 | 本人、配偶者 |
| 学生納付特例 | 128万円+38万円(原則)×扶養親族等の数 | 本人のみ |
| 障害者、寡婦、ひとり親 | 135万円 | – |
老齢基礎年金との関係は?
納付猶予されていた期間は、老齢基礎年金の受給資格期間(10年)には算入しますが、年金額の計算には反映されません。10年以内に追納する必要があります。保険料の納付が猶予されているだけです。
納付猶予制度は、令和12年6月までの時限措置です。
| 老齢基礎年金の 受給資格期間 | 老齢基礎年金の 年金額への反映 | 障害年金・遺族年金 受給期間への算入 | |
| 全額納付 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 全額免除 | 〇 | 2分の1※ | 〇 |
| 4分の3免除 | 〇 | 8分の5※ | 〇 |
| 半額免除 | 〇 | 4分の3※ | 〇 |
| 4分の1免除 | 〇 | 8分の7※ | 〇 |
| 学生納付特例 | 〇 | ✕ | 〇 |
| 納付猶予 | 〇 | ✕ | 〇 |
| 未納 | ✕ | ✕ | ✕ |
※平成21年4月以後の国庫が1/2負担する期間
それでは過去問いきましょう
問1. 学生納付特例による保険料納付猶予の適用を受けている第1号被保険者が、新たに保険料の法定免除の要件に該当した場合には、その該当するに至った日の属する月の前月から、これに該当しなくなる日の属する月までの期間、法定免除の適用の対象となる。
過去問 令和5年 国民年金法
問2. 平成27年6月分から平成28年3月分まで保険料全額免除期間(学生納付特例の期間及び納付猶予の期間を除く。)を有し、平成28年4月分から平成29年3月分まで学生納付特例の期間を有し、平成29年4月分から令和元年6月分まで保険料全額免除期間(学生納付特例の期間及び納付猶予の期間を除く。)を有する者が、令和元年8月に厚生労働大臣の承認を受け、その一部につき追納する場合は、学生納付特例の期間の保険料から優先的に行わなければならない。
過去問 令和1年 国民年金法
問3. 前年の所得(1月から3月までの月分の保険料については、前々年の所得。以下本問において同じ。)がその者の扶養親族等の有無及び数に応じ一定額以下の学生である第1号被保険者については、その者の世帯主又は配偶者の前年の所得にかかわらず、国民年金法第90条の3の規定による学生納付特例の適用を受けることができる。
過去問 平成28年 国民年金法
問4. 学生納付特例事務法人は、その教育施設の学生等である被保険者の委託を受けて、当該被保険者に係る学生納付特例の申請に関する事務及び保険料の納付に関する事務をすることができる。
過去問 平成23年 国民年金法
問5. 国民年金法による保険料の納付猶予制度及び学生納付特例制度は、令和12年6月までの時限措置である。
過去問 平成23年 国民年金法
国民年金の強制加入の人が未納だと障害年金や遺族年金を受けられない可能性があります。事情があり保険料を納付できないときは、積極的に免除や猶予の制度を活用しましょう。所得要件は対象者(本人・世帯主・配偶者)の区分や額が違いますので、申請免除・学生納付特例・納付猶予制度で横断して整理しましょう。
この記事が参考になったら応援お願いします。↓


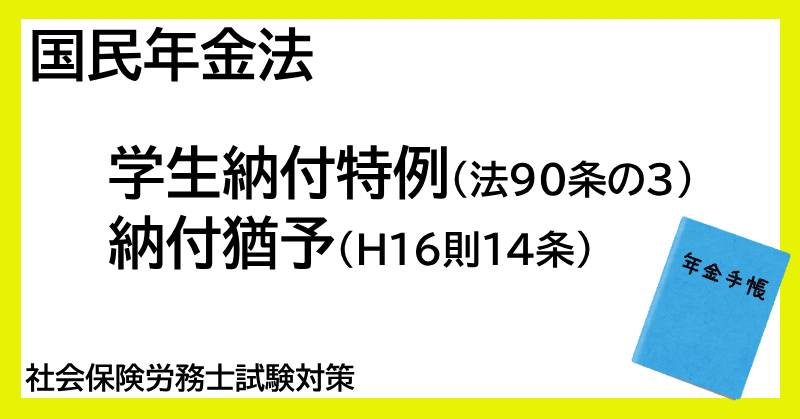
コメント