付加年金は、第1号被保険者の為の年金制度で国民年金の保険料に加えて毎月400円の付加保険料を納付することで自身が老齢基礎年金を受給る際、付加年金として200円×付加保険料納付済期間の月数の金額を上乗せして受け取ることができます。
付加年金の支給要件
付加年金は付加保険料に係る保険料納付済期間を有する者が老齢基礎年金の受給権を取得したときに、その者に支給されます。
条文を見てみよう
第43条(付加年金の支給要件)
付加年金は、付加保険料に係る保険料納付済期間を有する者が老齢基礎年金の受給権を取得したときに、その者に支給する。
第44条(付加年金の年金額)
付加年金の額は、200円に付加保険料に係る保険料納付済期間の月数を乗じて得た額とする。
第87条の2
第1号被保険者は、厚生労働大臣に申し出て、その申出をした日の属する月以後の各月につき、国民年の保険料のほか、400円の保険料を納付する者となることができる。
支給要件
- 付加保険料に係る保険料納付済期間を有する
- 老齢基礎年金の受給権を取得
第1号被保険者は希望すれば、毎月の保険料に追加して付加保険料として400円を納付することが出来て、老齢基礎年金の受給権を取得した時に200円に付加保険料に係る保険料納付済期間の月数を乗じて得た額が付加年金として支給されるんですね。
第1号被保険者が20歳から60歳まで480月(40年)付加保険料を納めたとします。その納付額は400円✕480月で192,000円です。付加年金の額は200円✕480月なので96,000円となります。つまり65歳から老齢基礎年金を受給したとしたら67歳の2年で元をとるということになります。
老齢基礎年金とは違い付加年金は改定率による改定の規定は適用されません。つまり物価や賃金の上昇と連動せずインフレに対応していませんが2年で元をとるというのはお得かと思います。
老齢基礎年金との関係
付加年金は老齢基礎年金と必ずセットで支給されます。なので老齢基礎年金がその全額につき支給が停止されているときは、その間、その支給は停止されます。
問1. 付加年金は、老齢基礎年金の全部又は一部が支給を停止されているときは、その間、その支給が停止される。
過去問 平成20年 国民年金法
解答
問1. ✕ ちょっとした引っ掛けですね。老齢基礎年金がその全額につき支給が停止されているときは、停止されますが、一部が支給を停止されているときは停止されません。
支給の繰上げと繰下げとの関係
老齢基礎年金の支給の繰上げの請求又は繰下げの申出を行うと、付加年金の額も老齢基礎年金と同じ割合で減額または増額します。
老齢基礎年金とセットと記憶しておくと良いですね。支給開始も同じ、全額が停止されると付加年金も停止、繰上げ・繰下げも同じ率で変動。
問2. 第1号被保険者期間中に15年間付加保険料を納付していた68歳の者(昭和27年4月2日生まれ)が、令和2年4月に老齢基礎年金の支給繰下げの申出をした場合は、付加年金額に25.9%を乗じた額が付加年金額に加算され、申出をした月の翌月から同様に増額された老齢基礎年金とともに支給される。
過去問 令和2年 国民年金法
解答
問2. ✕ 昭和27年4月2日生まれの人が65歳に達するのは昭和92年4月1日。平成換算すると92-63で平成29年になります。繰下げの月数の計算は「受給権を取得したした日の属する月から繰下げ申出した日の属する月の前月」ですので、平成29年4月から令和2年3月までは36月、増額率は1000分の7で36月 × 7/1000 = 252/1000 = 25.2%となります。
過去に問われた論点
国民年金基金との関係
国民年金基金も付加年金もどちらも、第1号被保険者の老齢基礎年金の上乗せの為の任意加入制度ですが同時加入は認められていません。
よって、国民年金基金の加入員となったときは、その加入員となった日に付加保険料を納付する者でなくなる旨の申出をしたものとみなすとされています。
保険料免除者は付加保険料を納付出来る?
付加保険料は第1号被保険者が希望すれば納付出来るのですが、除かれている人がいます。その一部の額につき保険料を納付することを要しないものとされている者及び国民年金基金の加入員です。
具体的には、
- 法定免除
- 申請全額免除
- 4分の3免除、半額免除、4分の1免除
- 学生納付特例、納付猶予
- 国民年金基金の加入員
注意点としては、産前産後期間に係る保険料免除者は付加保険料を納付することが出来るという点です。産前産後期間の保険料免除は所得の有無に関係なく保険料の負担を免除する規定なので付加保険料は納付出来ます。
任意加入被保険者も付加保険料を納付出来ますが特例任意加入被保険者は出来ません。
問3. 60歳から任意加入被保険者として保険料を口座振替で納付してきた65歳の者(昭和30年4月2日生まれ)は、65歳に達した日において、老齢基礎年金の受給資格要件を満たしていない場合、65歳に達した日に特例による任意加入被保険者の加入申出があったものとみなされ、引き続き保険料を口座振替で納付することができ、付加保険料についても申出をし、口座振替で納付することができる。
過去問 令和2年 国民年金法
問4. 日本国籍を有する者その他政令で定める者であって、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の任意加入被保険者は、厚生労働大臣に申し出て、付加保険料を納付する者となることができる。
過去問 令和2年 国民年金法
解答
問3. ✕ 任意加入している者が65歳に達し、老齢基礎年金の受給資格要件を満たしていない場合は特例任意加入の申出があったとみなされますので、前段は正しいです。ですが、特例任意加入被保険者は付加保険料を納付することは出来ませんので間違いとなります。特例任意加入は老齢基礎年金の受給資格が目的ですので年金を上乗せする付加保険料の制度はそぐわないと言うことだと思います。
問4. 〇 任意加入被保険者は付加保険料を納付できますので正しいです。
付加年金の受給権は「死亡」したときのみ失権します。老齢基礎年金に付加して支給される年金なので付加保険料を納付していたとしても、障害基礎年金や遺族基礎年金などを受給したとしても支給されません。また、死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間係る死亡日の前日における付加保険料に係る保険料納付済期間が3年以上である者の遺族に支給する死亡一時金の額には、8,500円が加算されることも忘れずに。付加保険料は前納も可能です。
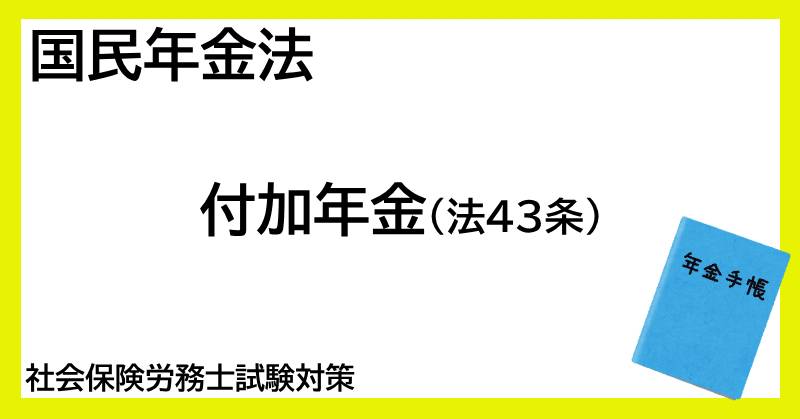
コメント